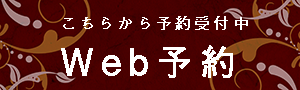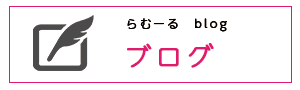よもぎは【ハーブの女王】と呼ばれ 古来から日本人に愛されてきました。
よもぎは飲んで良し!食べてよし!付けて良し!浸かって良し!蒸して良し!と 五拍子揃った薬草なのです。
漢方名では艾葉(ガイヨウ)と呼ばれていて その効果や栄養価の高さから 万能薬とも言われる程なのです
《よもぎにまつわる話》
ヨモギはキク科ーヨモギ属に属する植物で、本州から九州の日本各地と朝鮮半島の野原や道ばたや
民家の庭先で普通に見られる多年草の植物です。
ヨモギは大伴家持が詠んだ歌が万葉集 巻 十八の長歌で記載されています。
大伴家持の歌では菖蒲と一緒にヨモギが詠われており、昔はヨモギと菖蒲の香りには邪気を
追い払う力があると信じられていました。
ヨモギは薬食草と言われ、煎じて服用する薬やお灸の材料としての薬にもなり、ヨモギ餅やお浸し、
天ぷらにして食する事も出来る便利な植物です。
ヨモギの茎葉を丹念に揉んで作るのを「艾(モグサ)」と言い、昔から石臼で何度もひいて
製造しました。
お灸をすることを「灸(ヤイト)をすえる」と言いますが、「ヤイト」は元々「ヤケド」から変化した
言葉と言えます.
ら・むーる取り扱い薬草湯
よもぎ
★体の温まり方がぜんぜん違います
★冷え性さん是非お試しください
《昔ながらの言い伝え》
血行促進・肩こり・腰痛・美 肌効果
疲労 回復
《ご使用方法》
☆お風呂にそのまま入れるか、鍋などで一度煮出したものをお風呂に入れてください。
☆肩や腰など痛みがある部分にパックを当ててください。
《使用上の注意》
※ホーローのお風呂は着色する場合がありますので使用後は早めに洗浄してください。
※残り湯は洗濯に使えますがすすぎは真水をお勧めします。
※高温多湿を避けて保存してください。
《成分》 精油と酵素や多糖類、ビタミンA、B1、B2、C、各種ミネラルなど
《よもぎを煎じて服用した場合の効果》
血行促進、冷え性の解消、止血、不正出血、月経異常の解消、
便秘の解消、骨粗鬆症の予防、血圧の安定
艾葉と他の薬草(ドクダミ、ヨモギ、麦茶など)と一緒に煎じて服用しても良い。
また生のヨモギの葉を揉んで出血している患部に当てていると止血する。
《入浴剤として使用した場合の効果》
ヨモギの入浴剤は神経痛、腰痛、打ち身、捻挫、痔に効果がある。
ももの葉湯(べビーバス)
沐浴用20回分
★天然の桃の葉が赤ちゃんのお肌を優しく守ります
使用方法①
ベビーバスに本品1包を入れ熱めのお湯を注ぎます。
薬草成分が十分出ましたら冷まして温度調節
しながら赤ちゃんを沐浴させます。
使用方法②
鍋に本品1包を入れ煮立たせ成分を抽出します。
抽出した桃葉エキス(液)をペットボトルなどに
取り沐浴剤として使用する。
おしりふきにも使用できます。
《昔ながらの言い伝え》
菌の繁殖を防ぐ作用や
解熱作用、日焼け、あせも、湿疹、かゆみなどの炎症を
抑える作用があります。
お肌をスベスベにします。
《成分》
シュウ酸マグネシウム、カリウム塩、タンニン、アミグダリンなど
《ももを煎じて服用した場合》
オ血が原因の腹痛、炎症などを鎮める作用
があり、月経困難、月経痛、下腹部痛、便秘などに効果がある。
桃仁と他の薬草(ドクダミ、ハトムギ、玄草、麦茶など)と一緒に煎じて服用しても良い。
《入浴剤として使用した場合の効果》
収れん作用、菌の繁殖を防ぐ作用、消炎、解熱作用、強い紫外線による
日焼けの炎症やあせも、虫刺され、湿疹等肌のトラブルに効果がある。
ゆず湯
★冬の乾燥肌、
お肌をスベスベにしたい方是非お試しください!
柚子の果皮果肉使用 全部丸ごとつぶしました!

《昔ながらの言い伝え》
血行促進・美 肌効果・乾燥肌、かゆみに
リラックス効果
《ご使用方法》
☆お風呂にそのまま入れるか、鍋などで一度煮出したものをお風呂に入れてください。
☆肩や腰など痛みがある部分にパックを当ててください。
《使用上の注意》
※ホーローのお風呂は着色する場合がありますので使用後は早めに洗浄してください。
※残り湯は洗濯に使えますがすすぎは真水をお勧めします。
※高温多湿を避けて保存してください。
かゆみ、冷え、肩こり、腰痛、疲労回復に…
身体を芯から温めお肌をスベスベにします